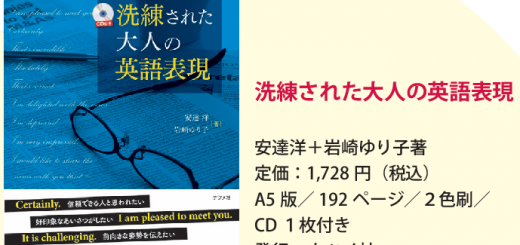Sep. 20th(Saturday) a.m.8:25 @ JJ Bean on Alberni st.
コーヒーカップの気球が行き着く先は、ほんとうの自分に出逢える“空 Ku:”のせかい。
今日もまた、バンクーバーのどこかのKu:Cafeで、誰かが小さな旅に出ます。
Alberni沿いのJJ Beanが好きな理由はふたつある。ひとつはガラス張りの2階席から通りが眺められること。そしてもうひとつは、ハムとチーズをはさんだTurnover。『Turnover:転覆、どんでん返し』。このおかしな名前の、だけど意外と美味しいものの存在を教えてくれたのはChrisだ。Chrisとは半年前に卒業した英語学校で知り合った。「きみの靴、いいね。イチゴみたいで」。それが彼の第一声だった。赤に白のドットが入ったエナメルのサンダルは確かに一番のお気に入りだったので、わたしは「ありがとう」と彼を見上げて笑った。彼も笑っていた。
そして、わたしたちは始まった。
Chrisは南米に浮かぶ島からやって来た留学生だったが、クラスの誰よりも背が高かった。見上げるたび、その広い肩の向こうに、彼を育んだ島の空が見える気がした。「ぼくの国ではイチゴはあんまり見かけないんだ、希少品なんだよ。だからきみの靴を見た時、ついおいしそうって思っちゃった」。ミディアムサイズのラテをアーモンドミルクでオーダーし、たっぷりのシナモンを振りかける。もちろんTurnoverも。終わりかけた夏の休日の朝は静かで、Bute street の交差点が見下ろせる特等席が空いていた。黒い革張りの椅子に腰掛け、ラテを一口飲む。ここのラテはソイでもアーモンドミルクでも、フォームがとてもきれいなのがいい。ガラスの向こうの交差点は、夜の間に降った雨で濡れている。点滅する青信号。ブレーキランプと赤信号。音楽のように規則正しいリズムに従って、人々は立ち止まり、歩き出す。
「あの二人は恋人だと思う?」並んで信号待ちをする男女を眺めながら、Chrisによく聞いたものだ。「I don’t think so.」。信号が青になり、横断歩道を渡ると、二人はまったく別の方向へ去っていった。この賭けはわたしたちのちょっとした遊びだったが、いつでもChrisが勝つのだった。「簡単だよ。空気の色が違うもの」。空気の色ってなんだろう。ハグしたときの肩越しに見える、その人だけの空の色? 皿に残ったTurnoverの欠片をつまんで口に運ぶ。「わざわざ拾わなくたって、ここについてる」。長い指が、唇に触れる瞬間が好きだった。
最後に会った日、わたしたちは同じ交差点で信号待ちをしていた。「帰ることにしたんだ」。別れ話にはとうてい似つかわしくない、いつもの笑顔でChrisが言ったので、その時初めて、彼の肩の向こうの空を少しだけ呪った。「イチゴのない国に?」。信号が青に変わると、Chrisは少しかがんでわたしにキスをした。何も言わないまま手をつなぎ、交差点を渡る。シグナルが、やけに鮮やかにまぶたの裏に映えた。「ありがとう」。わたしはChrisを見上げて笑った。彼も笑っていた。
そして、わたしたちは終わった。

原田章生: 愛知在住、絵描き/音楽家。 http://homepage3.nifty.com/harada-akio/
あの時、JJ Beanの2階席から誰かがわたしたちを眺めていたら、ふたりの “空気の色”は何色だったのだろう。赤信号と青信号みたいに、重なり合うことなく点滅していたのだろうか? まだ少しあたたかいTurnoverをかじりながら、ふと思う。
「I don’t think so.」。きっと誰の色も、瞬きうつろいながら、日々と交じり合いながら、ただ続いていく。ほんとうはひとつの色として、つながっている。虹みたいに、あいまいに優しく。唇にくっついたパイ生地の欠片をひろってくれる指は、どこか遠い青の下へ行ってしまったけれど、確かにここに “在った”。それは消えることなく、わたしの一部として、今も“在る”。瞬間ごとに生まれ変わる、自分だけの空の色を背に、わたしはきっとまた誰かと出逢って笑い合い、並んで交差点に立つだろう。そしてその人の肩越しの空を愛したり、呪ったりするのだ。それは、とても素敵なことのような気がする。